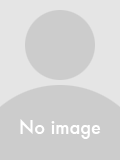論文
|

|
哲学者としての初期ルドルフ・シュタイナーによる「純粋経験」概念が、フッサールによる「現象学的還元」の概念に影響を与え、その原型となった可能性が高く、しかもフッサール「現象学」において展開される認識論は、随所でシュタイナーのそれへの詳細な注釈としての様相を呈している。そうした事例を追いつつ、『考へるヒント』・『考へるヒント2』周辺の小林秀雄の著作が、シュタイナーの純粋経験概念をなぞりつつも、フッサールがそれを注釈的に受容した箇所をも踏襲し、批評において「現象学的還元」を行おうとする側面をもつものであった事実を検証する。これが『本居宣長』執筆の要因にもなったと考えられる。以上の調査結果を、小林の批評のありかたが、西洋思想史に立脚して、その新しい局面を開こうと目論んだものであった事実を裏付けるための基礎作業として提出したい。 |